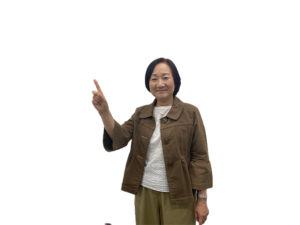B/Cが1.01→1.2⁉ 東京外環道事業再評価
10月18日、東京外かく環状道路(東名~関越)(以下、東京外環道)予定地の調布市の住宅地での陥没事故から5年が経過しました。
前のブログで前回の事業評価から5年後の今年度に次の再評価が公表されるはずだが、いまだに公表されていない旨を記しました。
練馬区議会第三回定例会中にも議会で取り上げましたが、担当課長からの答弁は「今年度中には公表されるはず」のみでした。
10月9日(木)、東京外環道の再評価について審議する、2025年第3回関東地方整備局事業評価監視委員会が開催されました。
資料はこちらをご覧ください
事業再評価とは
国土交通省は、事業再評価の目的を次のように示しています。
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、再評価を実施する。再評価は、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後長期間が経過している事業等の評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するものである。
B/C(費用便益比)が1.01から1.2へ
前回、2020年7月の事業評価では、事業化当初算定された事業費1兆2820億円が2倍近くの2兆3575億円になること。B/Cが1.01であることが公表されました。
B/Cは、1を割れば「採算割れ」を表します。
この5年間に陥没事故に対する地盤補修や住民への補償、複数のトラブルへの対処に要した費用が発生しており、B/Cは当然、1を切るものと予想していましたが、結果は1.2。
経済効果や渋滞緩和、羽田空港からアクセス向上などさまざまなメリットをアピール、試算してB/Cを改善させたのではないかと疑義を感じます。
事業費は、5年前から更に約4050億円増え、約2兆7625億円。計画当初の1兆2800億円の2.15倍であることがわかりました。
しかし、陥没事故原因と対策についてはNEXCO東日本と鹿島 JV の負担割合が決まっていないとして、事故処理関連費用は含まれていない。また、青梅街道インターチェンジ 拡幅部の工法変更の費用増加分も含まれていないとのことです。
また、現在すすめられている地盤補修工事は、完了したのはおよそ半分の範囲にとどまっていると報道されました。
世田谷から掘進している2基の本線シールドマシンは、陥没事故を受けて東京地方裁判所が「具体的な再発防止策が示されていない」などとして工事の中止を命じ、掘進再開の見通しがたっていません。
工期は2030年度までとしていますが、5年間で完成できるのか大いに疑問です。
区内でも振動、騒音などによる健康被害が
東京外環道の南端、世田谷からの地下トンネル工事による陥没・空洞事故と騒音・振動・低周波音による家屋損傷と健康被害の訴えがありました。
北端の大泉ジャンクション部から南進する2基のシールドマシンは、現在、青梅街道インターチェンジ計画地付近まで進んでいます。その周辺の住民からも、振動・騒音による健康被害を訴える声が届いています。
第三回定例区議会の決算特別委員会の質疑の中で、東京外環道の事業再評価についての区の考えを質しました(その時点では、監視委員会の開催日程が不明だった)。
「今回のB/Cの結果に関わらず、その推進の姿勢に変わりありません」と答弁。
大深度法は廃止へ
「地上には影響しない」と始まった大深度のトンネル工事によって、健康被害や家屋の損傷など多くの住民に影響が出ています。また、大きく人生を狂わされた方も少なくありません。一刻も早く、大深度地下法を廃止すべきです。
10月9日の事業評価監視委員会の再評価対象事業は東京外環道含めて3件。そのうちの2件はその日のうちに「事業継続」が了承されましたが、東京外環道は次回の委員会で引き続き審議を行うことになりました。
どのような判断が示されるのか、注視していきます。
以下、資料より抜粋。赤いマーキングはやないが加筆。