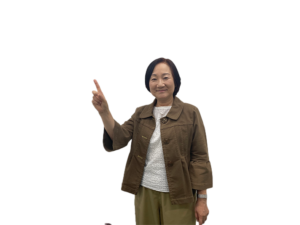「香害」対策のアプデを ~第三回定例会報告~
学校給食の白衣が各家庭で使用する洗剤や柔軟剤などで強い香りを放ち、それによって「気分が悪くなる」「息苦しくなる」といった健康面でも影響が出ていることを度々取り上げてきました。
区は、症状を訴える児童・生徒に対して未使用の白衣を貸与したり、個人で購入することを許可するなど、各学校において個別に相談に応じていると説明してきました。
しかし、「給食の白衣の匂いで困っている。何とかしてほしい」「どこに相談したらよいのか分からない」といった保護者からの相談が後を絶ちません。
今定例会の決算質疑において、学校での香害、化学物質過敏症対策について取り上げました。
区は「定期的に周知している」と答弁してきたが、「定期的」とはどのようなタイミングなのか?
担当の保険給食課長の答弁
・令和元年(2019年)に、区が国に先駆けて化学物質過敏症に関するリーフレット作成したのに併せ、各学校に柔軟剤などの香りの配慮についての周知を実施している。
・その際には、校内での啓発チラシの活用や、保健便りを通じた児童・生徒、保護者への情報提供、香りに関する違和感や症状を訴える児童・生徒への個別の配慮を求めている。
・以降も、国による啓発ポスターの作成や更新に合わせて実施している。
・今年7月には同様の内容を校長会で周知している。
国のポスター作成は2回あったので、2019年からの6年間で3~4回周知してきたと考えられます。しかし、毎年新入生を迎えますし、転校生もいることを考えると、最低でも1年に1回は各学校での周知が必要です。
着実に取り組むことを求めました。
子どもの香害はシックスクール問題
環境過敏症を研究している「日本臨床環境医学会」と「室内環境学会」が、2024年5月から2025年3月にかけて、全国約1万人の児童生徒を対象に「子どもの『香害』および環境過敏症に関する実態調査」を実施。その結果によると、小中学生の約10%が「香害による体調不良あり」と回答していること、年代が上がるにつれて増える傾向にあることが明らかになりました。また、体調不良の症状として、鼻詰まりや目の痛み・かゆみよりも、腹痛、吐き気、頭痛、関節痛、筋肉痛、脱力などが多いこともわかりました。さらに、約2%は香害のために不登校傾向にあるとのことです。
症状が出るほとんどが教室であることから、香害で学習環境が損なわれていると考えられます。
文部科学省は、児童生徒の心身の健康を守り、「学ぶ権利」を保障する責任があります。子どもの香害は、新たな「シックスクール問題」として対策すべきです。
シックスクール対策は、現在の基準において厳格に運用されています。だからこそ、文科省が新たな化学物質に対する基準の改定等に早急に着手し対策を講じるべきです。
一方で、困っている児童・生徒、心配する保護者が目の前にいるのですから、自治体としてできることを検討すべきです。
その一つが、学校の保健調査票の記載内容の見直しです。
さいたま市や宝塚市、船橋市、23区では大田区など、複数の自治体の保健調査票に香りの害や化学物質過敏症などの記述があり、記入例などで表記されています。
区は、「その他の欄にアレルギーなどについて記載することができる」と答弁しましたが、保健調査票の具体的な表記は、被害当事者の記述を促すだけではなく、香りの害や化学物質過敏症を思い当たらない家庭や子どもたちへの啓発にもつながるものと考えます。
区の「香害」対策は周回遅れ
香害や化学物質過敏症の周知啓発を求める質問に対して、区は、いまだに「他自治体に先駆けて区独自のリーフレットを作成し、周知啓発に取り組んでいる」という答弁を繰り返しています。
確かに2019年当時は、23区で初めての取組でしたが、その後、全国的に香害の対策に取り組む自治体が拡がりました。さらに、もっと踏み込んだ内容をホームページに掲載する自治体も増えています。
残念ながら、区の取組は周回遅れと言わざるを得ず、アップデート(更新)が必要です。
区民の健康を守る視点で対策を講じることを求めました。